![]() Contact us 24/7 from here
Contact us 24/7 from here
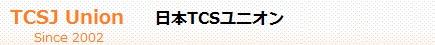
![]() Contact us 24/7 from here
Contact us 24/7 from here
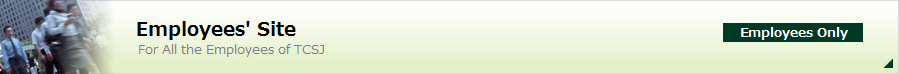
災害補償規程
第1条 (本規程の目的)
この規程は、日本TCSユニオン(以下「組合」という。)の次条に定める者が被った組合活動中の傷害または疾病(以下「傷病」という。)に対して次の各号の補償について定めることにより、組合活動の円滑な運営および傷病を被った者の救援を図ることを目的とする。
(1) 災害死亡補償
(2) 後遺障害補償
(3) 療養補償
第2条 (適用範囲)
本規程は、組合が作成、保管する名簿に記載された次の各号に該当する者(以下「本人」という。)に適用する。
(1) 組合員
(2) 組合職員
(3) 組合主催の行事に参加中の者。組合員であると否とを問わない。ただし、組合が行事開催前に作成し保管する行事参加者名簿に記載された者に限る。
第3条 (用語の定義)
本規程において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとする。
(1) 「傷害」とは急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除く。)を含む。
(2) 「疾病」とは、急性虚血性心疾患(いわゆる心筋梗塞)、急性心不全等の急性心疾患、くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患、気胸、過換気症候群等の急性呼吸器疾患、細菌性食中毒、熱中症(日射病および熱射病等)、低体温症、脱水症をいう。
(3) 「組合活動中」とは、組合の機関(大会、委員会、執行委員会等をいう。以下同様とする。)の決定に基づく指令、指示、通達による組合業務に従事中および組合の機関の決定に基づき組合が主催または共催する行事に参加中の状態をいう。
組合業務に従事するためまたは組合行事に参加するための、往復途上および旅行行程中は組合活動中とする。
(4) 「公的給付」とは次の給付をいう。
① 労働者災害補償保険法に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度によって支給される障害に対する給付
② 次のいずれかの法律その他の社会保障法令によって支給される障害に対する年金給付
イ.厚生年金保険法
ロ.国民年金法
ハ.国家公務員共済組合法
ニ.地方公務員等共済組合法
第4条 (災害死亡補償-弔慰金)
組合は、本人が第1条の傷病を被り、その傷病により、傷病を被った日(傷害については事故日、疾病については医師(本人が医師のときは、本人以外の医師をいう。以下同様とする。)の診断による発病の日をいう。以下「傷病発生日」という。)から180日以内に死亡した場合には、次のとおり弔慰金として本人の法定相続人に給付する。
| 弔慰金 |
2,000 |
万円 |
第5条 (労働組合活動中または参加中の認定)
(1) 前条の給付には、中央執行委員会により、本人が第1条の組合活動中に前条の傷病を被ったことの認定を要する。
(2) 前項の認定が、その認定後最初に開催される中央委員会において承認されなかったときは、組合は弔慰金を給付しない。この場合において、既に弔慰金を給付していたときは、当会はその返還を請求することができる。
第6条 (後遺障害補償-障害一時金)
組合は、本人が第1条の傷病を被り、その傷病により、後遺障害を残したときは、障害一時金として次のとおり本人に給付する。
■第7条(1)による認定の場合、および第7条(2)①が労働者災害補償保険法に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度によって支給される障害に対する給付による認定の場合
|
障害等級 |
1級から 3級まで |
4級から 6級まで |
7級から 9級まで |
10級から 12級まで |
13級から 14級まで |
|
障害一時金 |
2,000万円
|
1,400万円
|
700万円
|
200万円
|
80万円
|
■第7条(2)①が厚生年金保険法・国民年金法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法その他の社会保障法令によって支給される障害に対する年金給付によって支給される障害に対する給付による認定の場合、および第7条(3)による認定の場合
|
障害等級 |
1級から 3級まで |
障害手当金に該当する場合 |
|
障害一時金 |
2,000万円
|
200万円
|
第7条 (後遺障害等級基準および認定)
(1) 前条の場合において、後遺障害の原因が傷害のときは、障害等級は労働者災害補償保険法施行規則別表1「障害等級表」の基準に従い認定する。この場合、傷病発生日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、傷病発生日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき認定する。
(2) 前条の場合において、後遺障害の原因が疾病のときは、次の各号に従い障害等級を決定する。
① 公的給付における認定と同一の等級に認定する。
② 前号の認定後に、公的給付において前号の認定より上位の等級が認定されたときは、その上位の等級に変更して認定する。この場合、前号の認定に基づき既に障害一時金を給付していたときは、その上位の等級に基づく障害一時金の額との差額を追加給付する。
③ 第1号の認定が行われる前に、後遺障害の原因となった疾病を直接の原因として本人が死亡したときは、災害死亡補償に準じて補償を給付する。
(3) 前条の場合において、後遺障害の原因が疾病で、公的給付において等級が認定されないときは、厚生年金保険法施行令第三条の八および同法施行令第三条の九の基準に従い認定することができる。
第8条 (後遺障害と災害死亡の関係)
組合が障害一時金を給付した後、本人が後遺障害の原因となった傷病の結果として傷病発生日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、弔慰金の額から既に給付した障害一時金の額を控除した残額を給付する。
第9条 (弔慰金等の給付による損害賠償の減免)
組合が、弔慰金または障害一時金を給付したときは、組合は給付した金額を限度として、本人が組合に対して有する損害賠償の責を免れる。
第10条 (療養補償-入院見舞金)
組合は、本人が第1条の傷病を被り、その治療のために入院したときは、入院日数1日につき次の金額を入院見舞金として本人に給付する。ただし、入院見舞金の給付日数は、180日を限度とし、かつ、傷病発生日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては入院見舞金を給付しない。
| 入院1日につき |
10,000 |
円 |
第11条 (療養補償-手術給付金)
前条の場合において、傷病発生日からその日を含めて180日以内に、本人が治療を直接の目的として別表に掲げる手術を受けたときは、入院見舞金の日額に手術の種類に応じて別表に掲げる倍率(2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率)を乗じた額を、1回に限り手術給付金として給付する。
第12条 (療養補償-通院見舞金)
組合は、本人が第1条の傷病を被り、その治療のために通院したときは、通院日数1日につき次の金額を通院見舞金として給付する。ただし、通院見舞金の給付日数は90日を限度とし、かつ、傷病発生日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては通院見舞金を給付しない。
| 通院1日につき |
7,000 |
円 |
第13条 (補償を行わない場合)
組合は、次の各号の傷病に対しては、補償を給付しない。
(1) 本人またはその法定相続人の故意または重大な過失による傷病。ただし、補償を給付しないのは本人の被った傷病に限る。
(2) 本人の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による傷病。ただし、補償を給付しないのは本人に被った傷病に限る。
(3) 本人の麻薬、あへん、大麻、覚せい剤またはシンナー等の使用による傷病
(4) 本人が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒によって正常な運転できないおそれがある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故による傷病
(5) 他覚症状のない本人の感染
(6) 頚部症候群(むちうち症)または腰痛で他覚症状のないもの
(7) 本人の妊娠、出産または早産
(8) 本規程発効日の直前12ヶ月以内に、医師の治療を受けまたは治療のために医師の処方に基づく服薬をしていた疾病と因果関係のある急性心疾患・急性脳疾患・急性呼吸器疾患。ただし、本規程発効日から36ヶ月を経過したとき以降に発生した疾病については、この限りでない。なお、本規程発効日において組合に未加入の者については、「本規程発効日」を「組合に加入した日」と読み替えて適用する。
(9) 前号の規定にかかわらず、第2条(適用範囲)第2号の規定により、本規程の対象となる組合員以外の者については、当該行事参加日の直前12ヶ月以内に、医師の治療を受けまたは治療のために医師の処方に基づく服薬をしていた疾病と因果関係のある疾病
(10) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)による傷病
(11) 核燃料物質(使用済核燃料を含む。以下この号において同様とする。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故による傷病
(12) 前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故による傷病
(13) 第11号以外の放射線照射または放射能汚染による傷病
第14条 (請求手続き)
本人またはその法定相続人が、本規程に基づく補償の給付を請求する場合には、次の各号の書類を事務局に提出しなければならない。
(1) 傷害のとき事故状況報告書、疾病のとき罹患状況報告書
(2) 医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書または死体検案書)
第15条 (運用)
本規程は、中央執行委員会を事務局として運営する。
第16条 (発効日)
本規程は平成27年10月 1日から実施する。
(注)上記の「手術」とは、医師が治療を直接の目的として、メスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいいます。